第十二話 桧原湖とケーキの宴
「俺は二十五歳で結婚する」
私は以前より周囲にこう宣言していた。
昭和三十六年前半。この年の九月で二十六歳になる私は、まさ子に熱烈かつ強引なプロポーズをしていた。今思えば、まさ子の都合などお構いなしに、とにかく押して押して押しまくっていたと思う。
「まさ子、俺と結婚しろ」
「えぇ??」
昇から遺伝した細く奥まった私の目は真剣で、まさ子に結婚を迫った。
私は『昭和の男』だ。昭和の男にムードなどというしゃれた言い回しは不要だ。私が言えばその通りになる。ならないなら、そうなるまでひたすら押し続けるだけだ。
当時、サークル活動でもリーダーを務めており、職人としても成長し、すべてにおいて順風満帆だった私は、様々な活動においても中心的存在としてモテモテだった。そのため自分に絶対の自信を持っており、私と結婚できるなんて光栄に思えとばかり、上から目線でまさ子に猛烈プロポーズしたのである。
私は周りに宣言していた以上、正当化させるためにこの年の前半はとにかくまさ子を自分の女房にするため必死だった。

「尾上さん、ごめんなさい。まだ家族を養わなければならないの。もう少し考えさせて」
当時、沼家を支える長女として必死に働き、家庭を支えていたまさ子はなかなか首を縦に振らなかった。
「俺から結婚を申し込まれて受けないなんてありえないぞ」
私はひたすら上から目線だった。
まさ子が私に惚れているのは間違いないし、沼家の弟たちが納得すればいいのだろう、と、当時池袋のバラック小屋に住んでいた、まさ子の親や弟たちにも会いに行き説得した。
「自分はもうすぐ工場で全ての製品を任してもらえる仕上工になります。まさ子さんを不幸にすることはありません。必要であれば沼家にも援助します」
彼女はその熱意についに応えてくれた。彼女はまだ22歳だったが、私の思いを受け止め、結婚を決意してくれた。

しかし、まさ子は結婚後にこう語っている。
「この人は酒を絶対に飲まないというのがプロポーズを受けた決め手だった」
まさ子の父は酒癖が悪く、酔うとすぐに母に手を挙げていた。そんな父の姿を見ていたまさ子は、絶対に酒を飲まない人と結婚すると心に決めていたという。
ところが、尾上家は親戚中を探しても誰一人酒が飲めない。というより、飲んだら全員そろって寝てしまう体質だった。これがまさ子にとってはまさに理想的だったのである。
もし当時、私が少しでも酒を飲んでいたら、彼女はプロポーズに決して首を縦に振らなかっただろう。
自分ではすっかり色男気取りで惚れさせたつもりだったが、それは大きな勘違いだった。まさ子が私の気に入ってくれたのは、昇とよしから受け継いだ体質だったのである。
こんな恥ずかしいことは直接まさ子には言ったことがないが、こうして当時一番かわいいと思っていたまさ子に強烈アタックして何とか結婚に漕ぎつけられたのだが、結婚した後は白々しく、
「一番不細工なのを選んでしまった」
と冗談ぽく言うようにしていた。
これにはまさ子からよく怒られたものである。
私たちは、私が二十六歳になる直前の昭和三十六年九月初旬に結婚式を挙げた。
式自体は質素だったが、当時としては珍しい会費制にして、ひとり二百五十円ずつ払ってもらい、ケーキを振る舞うという形にしたことでたくさんの友達を呼ぶことができ、盛大に行われた。恐らく百人近くはいたと思う。まさ子も会社や新宿の緑の会の友達を大勢招待していた。
まさ子のウエディングドレス姿は本当にきれいだった。友達も親戚も皆、瞳の大きなまさ子に見とれていたのをよく覚えている。

今思い出しても、あのときの二人は確かに熱かった。互いしか見えない──まさに二人だけの世界だった。
結婚式を挙げたあと、私たちはすぐに新婚旅行へと出掛けた。向かった先は、福島の裏磐梯。都会の喧騒から逃れ、ただ静かに、誰にも邪魔されずにふたりきりでいられる場所を求めていた。
秋晴れの空はどこまでも高く澄み、空気はひんやりとしながらもどこか甘かった。私たちは磐梯山の山道を歩いていた。足元には落ち葉が敷き詰められ、踏みしめるたび、やわらかな音が小さく響いた。周囲は驚くほど静かだった。遠くで鳥が一声さえずるだけで、世界全体が耳を澄ましているような、そんな沈黙があった。
「尾上さん、ちょっと待って。さすがに着いていけないわ」
息を弾ませながらそう言うまさ子の声が、森の静けさに溶け込むようにして響いた。
「わかった。もっとゆっくり行こうって。……お前も、もう“尾上さん”なんだけどな」
「あらやだ。じゃあ、なんて呼んだらいいのかしら?」
「好きに呼べばいいじゃないか」
「……じゃあ、“あなた”で」
「いや、ちょっとこっぱずかしいな。勘弁してくれよ」
そんなやりとりさえ、ここでは何か特別な儀式のようだった。ふたりとも生まれも育ちも都会で、人のいない場所に身を置くことに不慣れだった。けれど今、誰の目も届かないこの山道で、ただ私たちだけが歩いている。心の底から、世界に残されているのはこのふたりきりなのだと思えた。
風が草をなでるように吹き抜け、葉がささやく。木々の合間からこぼれる光が、ゆるやかにまさ子の頬を照らす。森の入り口では、土と苔の匂いを含んだ冷たい空気が肌をかすめた。
彼女の「はあ、はあ」という呼吸がすぐそばにある。その音に、私はふと実感する。ああ、私はこの女と所帯をもったのだ。そう思うと、胸の奥がじんわりと熱くなった。
木漏れ日を背に、まさ子が先を歩いてゆく。その細い背中が、光の粒に縁取られ、まるで夢の中の人物のように思えた。私はその姿を追いかけるように、ゆっくりと歩を進めた。
やがて、視界がぱっと開けた。そこは山頂だった。眼下には、鏡のように静まり返った桧原湖が広がっていた。湖は、まるで時間そのものが息をひそめているかのように、静かに光り輝いていた。
まさ子は、しばらく無言でその光景を見つめていた。湖面に映る空は、吸い込まれそうなほど青く、透き通っていた。かすかに笑みをたたえたまさ子の横顔を、私は見つめ続けていた。
それは、どんな風景よりも美しかった。
触れようとすれば崩れてしまいそうなほど儚く、ただ見ているだけで胸が満たされていくのだった。
「きれいね」
まさ子がそういうと私も答えた。
「あぁ、とってもきれいだ」
「って、どこ見て言ってるのよ。景色見てないじゃない。ふふふ」
「え?あぁ、景色もとってもきれいだな」
私は──湖の景色ではなく、その景色に心を奪われているまさ子を、黙って見つめていたのだった。
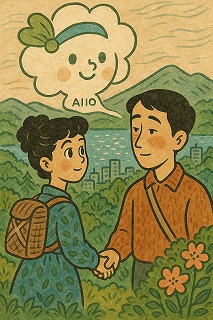
私たちは山の疲れを癒やすため飯坂温泉の宿へ向かった。
湯気に霞む湯船に身を沈めると、長旅の疲れがじんわりとほどけていく。
やがて部屋に戻ると、灯りはほんのりと落とされ、障子越しに月明かりが淡く滲む中、真新しい浴衣をまとったまさ子の大きな目を見つめる。
傷だらけの職人の手をその美しくも柔らかく小さな手にそっと重ね、私はそっと彼女を抱き寄せた。
「これからの生活が心配かい?」
「いいえ、ちっとも」
下ろしたばかりの浴衣に手をかけ、肌に触れる。温泉の余熱でほんのりと火照った彼女は、どこか儚くも美しかった。
温泉の熱さと夜の静寂が交錯する中で、息を合わせて静かに寄り添う私たちは、確かにそこに存在していた。
名残惜しさを胸に、私たちは湯の香りをまとったまま宿をあとにした。
帰りの列車で、まさ子は窓にもたれ、時折うとうととまどろむ。その寝顔を眺めながら、私はこの旅が終わることを惜しんだ。
「うえの~、うえの~ぅ、お忘れ物のないように・・・」
やがて東京に着いた二人は、打って変わって慣れた喧騒の世界に舞い戻って来て、そして、その中に紛れていく。
だが、心はまだあの夜のままだった。
二人は、すでに契約を済ませていた三軒茶屋のアパートに帰り、その日から二人暮らしが静かに始まった。
アパートは四畳半しかなく、とても狭かったが、二人にとっては世界のすべてだった。
窓から差し込む朝日で目を覚まし、肩を寄せ合いながら夜を迎える。小さなちゃぶ台で向かい合って食べる粗末な食事も、二人でいればご馳走になった。
布団を敷けば足の踏み場もなくなるほどの狭い部屋。それでも、手を伸ばせばいつでもまさ子がいる。それが何よりも幸せだった。
この部屋から、私たちは未来へと歩み出したのだ。

この部屋から私は目黒のムサシ電機に、まさ子は新宿のウィスキー工場に通い、地道にお金を貯め続けた。
この時代はとにかく貧しく、金がなかった。だが恐れるものは何もなく、未来はきっとよくなると信じて、お互いに寄り添いながら生きていたのである。
まさ子は後にこう語っている。
「あの頃は本当に何もなかった。『神田川』の歌詞がとにかく嫌いだったわ。あの歌がヒットした時、私はあの貧しかった日々を思い出してしまって……」
──若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたのやさしさが怖かった
ひとつだけ、歌詞と違いがあるとすれば、私は決してやさしくはなかったのかも知れない。
昭和のあの時代、優しい男などいなかったのだ。
(正確には、結婚して所帯を持った男は優しくなくなる。というべきか……)
それはまた別の話として後に語ろう。
<ホーム>