第七話 俳句と八ヶ岳
つるんで遊んでいた友達は警察に連行されていなくなってしまった。
私はムサシ電機の工場で歯車の一部のように、ただ黙々と時間をすり減らしていた。汗を拭く間もなく繰り返される単調な作業。その音にまぎれて、心の奥底から何かが軋む音が聞こえていた。
「このまま、俺は一生このままなのだろうか?」
ふと立ち止まったある日、ふいに目の前に広がったのは、未来が霞んで見えない断崖。そこに立ち尽くした私は、飛び移るべきツタを必死で探していた。
きっかけは入院だった。静かな病室で見つめた、川柳という小さな言葉の宇宙。
五七五に凝縮された世界に、なぜか心が強く惹かれた。「これかもしれない」と直感した。
退院後、かすかな希望をたぐり寄せるように、俳句の仲間を探し始めた。そんなある日、野沢に住む古い知人が、ぽつりとこう言った。
「自由が丘に、いい俳句の先生がいるよ」
その名は──間部隆。高校の国語教師だった。
ちょうどその頃、間部は『俳句会』という新たな同人誌を立ち上げようとしていた。
創刊号の参加者を募っていたそのタイミングに、私はまるで導かれるように門を叩いた。滑り込むように、その輪の中に加わったのだ。
俳句同人誌『炎群』──燃えさかる思いを抱いた者たちの群れ。その名に惹かれた。
五・七・五。たった十七音の、短くも深い詩。
川柳は、人の世の可笑しみや哀しみを詠む。何気ない暮らしの中の、ふとこぼれる笑い。人の弱さや滑稽さを、言葉でそっとすくいあげる。
一方、俳句は違う。
季節の移ろい、風の匂い、月の輝き──人間を超えた何か、見えない大きなものへのまなざし。俳句は、自然と人との「あいだ」を詠む詩だった。
同じ五・七・五でも、視線の向け方ひとつで、見える世界がまるで変わる。
人の世の機微に笑うのもいい。だが私は、それだけでは足りなかった。
空を見上げ、風に耳を澄ませ、そこに宿る何かを言葉にしてみたい。
それが、今の自分を越えてゆく唯一の道だと思った。
文学や風景に惹かれていた私は、自然と川柳ではなく俳句を選んだ。「趣味」と呼ぶには、少し背筋が伸びるような世界だった。それでも私は、その扉を開けてみることにした。
十七音の先に、新しい自分がいる気がした。
爽やかに プレスの音の ひゞきけり
──尾上義秋
私が俳句一年生として『炎群』の創刊号に載せた俳句である。
当時の私の心境が色濃く残されているのが自分でも実感できる。

工場の一日が始まり、静けさを破って響くプレス機の音。その重厚な金属音が、どこか清々しさを伴って耳に届く。「爽やかに」という意外な取り合わせが、単なる騒音ではなく、労働のリズムや、働くことの清冽さをも感じさせる。朝の空気を切り裂くように響くその音は、ものづくりの現場の息吹そのものであり、その瞬間に季節の清々しさと人の営みを重ねて詠んでいる。
(それぞれの私の句はこちらにまとめたいと思う。)
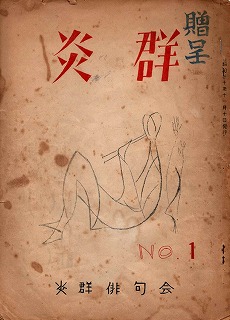
私は俳句の発表では読みは同じでもより俳句の季節感を出すため「義秋」の名を使うようにし、ここから私はこの名で生涯をかけて俳句にのめり込んでいく。
私にとっては日本語、そして俳句の師となり、厳しき導き手であり、何より、生きることと言葉を結びつけてみせたこの間部隆という師は、時には、私を鋭く切り捨てた。
「尾上君、君の日本語はめちゃくちゃだ」
「その言葉は生ぬるい。情景が全く頭に伝わってこない」
「自然を写すだけなら猿の方がまだましだ」
何しろ、私より年下の高校生も含めての叱咤だ。周りの高校生たちは私の句を聞いてはくすくすと馬鹿にするかの如くに笑っていた。
私は叩きつけられる言葉と、その失笑にただただ恥ずかしさと悔しさを噛み締めた。
だが、私は思った。
──ターザンもまた、ただ叫んでいただけではない。
──獣と闘い、森と語り、ただ一人で生き抜いたのだ。
ならば、私もまた、言葉という名のジャングルに分け入り、裸一貫で闘わねばならない。
炎群の会では、より自然と触れ合えるよう、間部隆師匠が声をかけ、吟行──つまり俳句を作る旅行を沢山企画してもらった。
尾瀬、上高地、野辺山高原、小諸の懐古園、奥多摩等・・・

都会暮らしで山や緑にはほとんど縁がなく、灰色になっていた私の心は、この間部隆師匠のお陰で、徐々に人間らしい色に染められていった。
山奥の小さき殻よかたつむり 義秋
ある日、八ヶ岳に登ることになった。
それまでは特別、山に興味があったわけじゃない。ただ、一歩山に踏み入ると、今までは当たり前に感じていた都会の埃っぽい空気と押し付けられるような雑踏から、完全に切り離せて自分が自然の一部になったような錯覚に陥る。
この頃から私は山を愛するようになる。
師匠は、女子高の先生でもあり、その高校の俳句部も指導していたのだが、今回のこの旅にその高校生たちも同行していた。
この山登りも、部員たちへの「実地研修」みたいなものだったようだ。
私は彼女たちよりも一回り年上だったため、格好つけてお兄さんの態度を取っていた。とびきり可愛い子に狙いを定め、軽口を叩いてみせたり、道端の花を摘んで手渡してみたり、いささか古風なアプローチもかけてみた。
師匠は振り返り、にやりと笑った。
「言葉で人を打つには、まず自分が本物を見て、骨身に刻め。机上じゃ何もわからんぞ」
その言葉に、私も含め、高校生たちは大げさにうなずいた。
昼食のあとの短い休憩時間、私は思い切ってその彼女に声をかけた。リュックのベルトを整えていた彼女の横に腰を下ろし、涼しげな風を装って言った。
「君、こんな山登りに来るとは思えないくらい可愛いね。……よかったら、帰ったあとも、僕と付き合ってみないか?」
冗談めかした口調にしたつもりだった。だが、自分でもわかっていた。本気だった。
都会の喧騒でも、職場の同僚でもなく、この純粋で柔らかそうな世界に自分が触れられたなら、自分の何かも変わるような気がしたのだ。
彼女は一瞬、こちらを見た。小さく首を傾けて、それから目を細め、少し笑った。
「えっ……あの、すみません、でも私……その、労働者の方って、ちょっと、恋愛とかは考えられないです」
その言葉には毒気も悪意もなかった。彼女にとっては、それが真実で、当たり前のことだったのだろう。
だけど、私の心には、その無垢さゆえの残酷さが深く突き刺さった。
「……ああ、うん。そうだよね」
とだけ答え、私は立ち上がった。
列に戻らず、しばらく一人で歩いた。胸の奥がきしんでいた。
労働者の方、という言い回しが、耳の奥で何度もこだまする。
彼女の口から発せられたそれは、まるで自分が土と油にまみれた、低い世界の住人であることを証明する刻印のようだった。
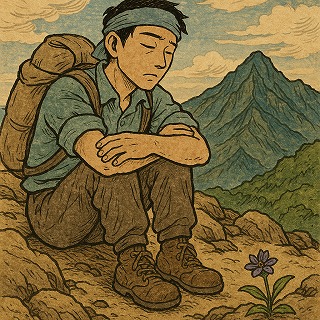
なんだ、自分は。俳句もろくに詠めず、知識もなく、ただ手を動かして稼ぐことしか知らない。
それを補うように、見よう見まねの手段に縋り声をかけ、自分の置かれている境遇で容赦なく断られて、打ちのめされている。
情けない。恥ずかしい。どうしようもない自分に、涙があふれた。
草のにおい、登山靴のきしむ音、山肌をなでる風。そのすべてが、自分の滑稽さを静かに照らしているように思えた。
師匠は、少し離れた岩陰から、こちらを見ていた。何も言わず、ただ黙っていた。
泣いていることには気づいているだろうが、師匠は顔をそらすでも、近づくでもなかった。
――それでよかった。
私はこの恥を、誰にも救われることなく、自分で受け止めるしかなかったのだ。
──本物を、見る。
──骨身に、刻む。
今の私のひとつひとつの経験が、積み重なっている実感を感じた。
師匠は、じっと私を見つめたあと、低く静かな声で言った。
「君はまだまだ日本語の勉強が足りない。いいか、高校生たちは、日中、君が機械と向き合っている時間も常に学んでいるんだ。それに、これからも大学に進んで、さらに日本語を深く学ぶだろう。……君は、彼らに追い付けるかい?」
その言葉は、胸に鋭く突き刺さり、一瞬、呼吸が止まるような感覚さえ覚えた。
(私は――なんて甘かったのだろう。)
今までは、どこかで「自分は頑張っている」と思い込んでいた。けれど、師匠の言葉の前には、その自負はあまりに軽く、脆かった。
もっと多くを学ばなければならない。昼夜問わず本当の意味で、自分を鍛えなければならない。
そして、ふと気づいた。彼女たちはろくに高校も行かず大学にも行っていない私を最初から見下していたのだ。
彼女ら高校生たちよりも、私は年齢が上というだけだ。知識も学も何もない。私は酷いコンプレックスを感じた。すでに大きく遅れをとっていたのだ。
可愛いね。なんて口説いてても、心の中では「勉強もできないおバカさん」と心の中で下に見られているに決まっている。
私は、ただぼんやりと学び続けるだけではいけない。やがて、追い付き追い越し、さらに教える側に立つほどになければ。と改めて思うのだった。
しばらくして、ふと、顔を上げた。
そこには、抜けるような青空だ。どこまでも高く、どこまでも澄んだ空。人の作ったものなどひとつもない、ただただ広大な世界が広がっていた。
やがて、頂上にたどり着くと、私は地べたにへたりこんで、ただ黙って息をついた。
ふと目を落とすと、小さな花が咲いている。岩陰に、風に吹かれながら、しっかりと。
それは名も知らぬ花だった。だが、なぜか目が離せなかった。
こんな過酷な場所で、それでも咲く。そのひたむきさに、胸を打たれた。
高山植物――厳しい環境に耐え抜くために、地面に這うように育ち、短い夏を全力で生きる、まさに生命の力強さの象徴である。
――私は自分の道を見つけないといけない。そしてどうにかして生き延びるんだ。
その思いが、胸に静かに灯った。
働くことに疲れたわけじゃない。生きることそのものに、立ち向かいたかった。誰かに認められるためでも、金を得るためでもない。自分の足で、自分の意志で立って、自分の人生を見つけ歩いていきたい。
山で見たもの、感じたことを、どうにか言葉にしたいと思うようになり、たまたま手に取った小林一茶という俳人の詩集に出会い、強く心を動かされた。
十七音。
たったそれだけの短い詩で、こんなにも人の心を打つ。
八ヶ岳で見かけた名も知らない高山植物の小さな花。この小さな命に、恥じないように。私もまた、ここから、歩き続けていこうと思うのであった。
<ホーム>